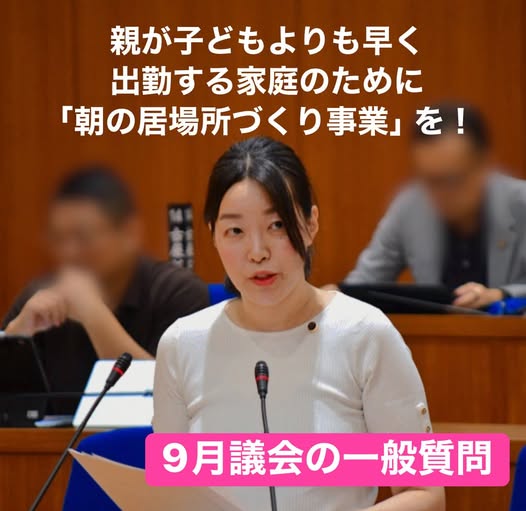】
こんにちは!
今日の雷雨、皆さん大丈夫でしたでしょうか?
子どもたちの下校時刻と雷雨が重なり、私も心配で気が気ではありませんでしたが、学校でしばらく預かってくださり、集団下校してくださるという対応の素晴らしさ…本当に感謝です
続いて一般質問テーマ②について紹介します!
皆さんは「朝の小1の壁」をご存じですか?
いま全国の共働き家庭で大きな課題になっています。
保育園時代は朝7時から子どもを預けられましたが、小学校に入ると登校は朝8時前後と遅くなります。
親が出勤のために子どもよりも朝早く家を出なければならない家庭が増えており、まだ6歳の子どもが、朝ひとりで鍵を閉めて家を出て小学校に登校する…こういう家庭が今、少しずつ増えています。
親は朝、「いってらっしゃい」と我が子を見送れない辛さと不安を抱えながら職場に向かい、子どもは小さな背中でその現実を背負って、1人で小学校に登校しています。
これは一部の家庭の問題ではありません。
こうした働き方の問題には、個人の努力だけではどうにもならない社会構造的な壁が立ちはだかっているのです。
このような背景を受けて、埼玉県志木市では県内初のモデル事業が立ち上がり、朝7時から子どもを預かる仕組みがスタートしました。
東京都品川区ではパンやおにぎりなどの提供も始まり、共働き家庭から大きな支持を得ています。今この「朝の居場所づくり事業」の動きは全国で急速に広がっています。
私もひとりの母親として、子育てをしながら痛感しているのは、「条件が整うのを待っていたら、いつまでたっても仕事と子育ての両立はスタートできない」という現実です。
本当は、自分のキャリアアップや、仕事のやりがいも諦めたくない。でも朝、子どもが一人で鍵を閉めて家を出る姿を想像するだけで胸が苦しくなる。
もし子どもが朝、安心して過ごせる場所があれば、親は安心して子どもを送り出して働けるのに…そんな悩みを抱えている保護者が戸田市にもたくさんいるはずです。
ある戸田市のお母さんからはこんな声が届きました。
「子どもが小学校に入学したらフルタイム勤務に戻したい。でも朝、こどもより早く家を出なければならないと思うと辛すぎて、フルタイム勤務は諦めざるを得ない。自分の夢もキャリアも手放すしかないのが本当に苦しい」
これは一人のお母さんの問題ではありません。同じ悩みを抱え、涙を飲んでキャリアを諦めている親がたくさんいるのです。
だからこそ行政が環境を整えることが必要です。
「いつか条件が整ったら働こう」。
みんな、そう願いながらも、子育てとキャリアアップのタイミングは重なり、その“いつか”は永遠にやって来ないのが現実です。
私自身も母親として痛感しています。
子育てと仕事はどちらも「待ったなし」であり、条件が揃うのを待っていては、いつまでも何もできない…
子育てと仕事の狭間で葛藤する、多くの母親が直面する社会的な壁ではないでしょうか。
だからこそ今、行政が受け皿となり、安心して働ける環境を早急に整えてほしいと思います!
志木市や東京都に続き、子育てファミリーや共働き世代の多い戸田市でも「朝の子どもの居場所づくり」事業を早急に導入してほしいと議会で要望いたしました!!
子どもが安心して朝の時間を過ごし、親も自分の夢やキャリアを諦めずに働ける。そんな未来を戸田市でも必ず実現していきたいと思います!!
一般質問を読んでくださった皆様からのご意見もお待ちしています!!
件名2:「朝のこどもの居場所づくり事業について」
【宮内の発言】
それでは、件名2:「朝のこどもの居場所づくり事業について」に入ります。
本日、私がご提案したいのは、「朝の居場所づくり」の導入についてです。戸田市はこれまで、都心へのアクセスの良さと、手頃な住宅価格の魅力によって、自然と子育て世代が流入し、増え続けてきました。かつては新築マンションが3,000万円代で購入できることも多く、若い世代にとって手の届きやすい街でありました。
しかし近年では、戸田市における新築マンション価格は6,000万円前後に上昇しています。このままでは、子育て世代の流入がストップしてしまい、街の活力が失われるのではないかと危惧しております。
だからこそ、今、戸田市に求められているのは、「都心へのアクセスの良さ」や「住宅価格の優位性」に頼らなくても「真に選ばれる街」へと転換することです。
そのためには、真に魅力のある政策を打ち出していく必要があります。その一つに「朝の居場所づくり」があります。
本市において、共働き家庭やひとり親家庭が増えるなか、小学校登校前のわずかな時間に、子どもを安心して預けられる制度は、今、戸田市の子育て世代に求められているニーズです。
私はこれまで、小学校入学を機に、親が仕事と子育ての両立が難しくなる「小1の壁」について、過去2回にわたり議会で取り上げてきました。
しかしながら、市民の声を伺う中で、放課後の「小1の壁」だけではなく、いま、「朝の小1の壁」が大きな課題となっていることを知りました。
先日も1通のメールをいただき、次のようなご相談をいただきました。「現在、小学1年生の子どもがいます。時短勤務を利用して働いていますが、なかなかフルタイム勤務に戻せません。なぜなら、フルタイム勤務に戻してしまうと、子供よりも早く家を出なければならず、子どもが朝一人で学校に行かなければならなくなるからです。その辛さを考えると、フルタイム勤務にはなかなか戻れません。自分の夢である昇格やキャリアアップをあきらめざるを得ず、毎日、苦しい気持ちで過ごしています。ぜひ戸田市でも、朝、子どもを安心して預けられる制度の構築をよろしくお願いします。」このメールを読んで、私も母親として強く共感しました。
子どもが学校に登校する際に、親が「いってらっしゃい」と見送れない辛さ、小学1年生の、まだ6歳の子どもが、あさ一人で鍵を閉めて家を出なければならない大変さを想像しただけで、葛藤する親の気持ちが痛いほど分かります。これは特定の一人の声ではなく、現代社会で働く多くの親が直面している課題です。
共産党の花井あきこ議員も前回の議会で、学童保育における朝の預かり時間について要望しており、重なる部分もありますが、花井あきこ議員にも同様の声が届いているということは、それだけ戸田市においても、子育て世代が朝の居場所を求めており、切実な願いが広がっている証拠であるとも言えます。
「朝の小1の壁」の背景には、小学校の登校時間と保護者の出勤時間のズレがあります。保育園時代は朝7時台から預けられたのに、子どもが小学校に入学すると、登校時間が8時前後と遅くなることで新たに生じる課題です。
私の近所には、小学校の先生をしているママ友がおり、話を聞くと、夫婦で出勤時間が早いので、親が子供より先に家を出なければならず、子どもは、通学班の集合場所に20分以上も早く行き、1人で先に待っているそうです。あさ子どもを送り出してあげたいけれど、どうしても夫婦ともに、子どもよりも早く出勤しなければならず、大きな葛藤や不安を抱えながら職場に向かっていると聞きました。これはまさに、個人の努力だけではどうにもならない社会構造上の大きな壁です。
今、こうした課題が表面化しており、埼玉県では大きな1歩が始まりました。埼玉県志木市では初めてのモデル事業を立ち上げ、朝7時から子どもを預かる仕組みを整備し、さらに和光市や行田市も試行的に事業を開始しました。
こうした朝の居場所づくり事業は、全国でも急速に広がりつつあります。神奈川県大磯町(おおいそまち)では、2016年から朝7時15分から子どもを預かる仕組みを始め、利用者はこの5年で倍増したそうです。大阪府豊中市(とよなかし)では、市内39校で朝7時から校門を開放し、利用している子どもの9割以上が「親が仕事に行くため」と回答しており、保護者からは「子どもの安全が確保されて、安心して仕事に行ける」と非常に高い評価を得ているそうです。東京都三鷹市では2023年から市内すべての小学校で朝7時半から校庭を開放し、シルバー人材センターが見守りを担うことになり、市民ニーズに対して、わずか5か月で制度化しました。
さらには東京都23区でも同様の動きが広がっており、豊島区では、来年度から市内22のすべての小学校で、学校の用務員さんによる朝の見守りを始める予定です。しかも追加の経費を一切かけずに「用務員の委託費だけ」で全校展開できる工夫をしています。品川区では、朝の居場所を提供するだけでなく、パンやおにぎりを無償で配るなど、いわゆる「朝食の提供」も行う予定で、この事業に伴う予算として、およそ5,700万円が令和7年度の当初予算案に計上されています。栄養面からも子どもを支える取り組みは、行政が家庭と地域を支える最新のモデル事業としても注目されています。世田谷区は小学校2校で見守りスタッフを配置し、2028年度には全校で導入予定です。杉並区や江戸川区も2025年度に試行を検討しており、港区では小学1年生を対象に「モーニングスクール」を始める予定です。
国としてもこの動きは広がっており、こども家庭庁の調査では、保護者のおよそ3割が「朝の居場所があれば利用したい」と回答しており、とりわけ都市部でのニーズが顕著であることが分かっています。東京都はすでに財政支援を制度化し、区市町村に人件費の3分の2を助成できる仕組みを整えており、今や「朝の居場所づくり」は都市部を中心として急速に広がっているのです。
だからこそ、都心に隣接する、子育て世代の多い戸田市においても、放課後の整備だけではなく「朝の居場所」の整備にも真剣に取り組み、働く親が夢やキャリアを諦めなくてもよい街づくりを目指して欲しいと思います。このような背景を踏まえ、通告に従い一般質問をさせていただきます。
件名2:「朝のこどもの居場所づくり事業について」
志木市では埼玉県内初の試みとして、小学校の開始前に児童を預かる「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」を実施し、これに続く自治体も増えている。本市においても、保護者が仕事で子どもより朝早く自宅を出なければならない家庭も増えており、同様の事業を求める声が多く寄せられているが、市の見解はいかがか。
【戸田市のご答弁】
志木市のモデル事業については、市立志木小学校の1年生から6年生までを対象に、学校敷地内に併設されている社会教育施設にて、午前7時から午前8時までの間、児童が過ごすことができるサービスとして、本年6月から開始されたものでございます。本事業は、埼玉県の「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」の補助金を活用した事業であることから、今後、県を通じ、実績など、様々な有用なデータが示されると考えております。こうした中、本市の朝の居場所事業のニーズにつきましては、先の6月議会の花井議員の一般質問において、学童保育室の朝の開室に関してお答えしたとおり、昨年度末に、この春小学校に入学する、公立保育園5歳児クラスの園児の登園状況を調べたところ、朝7時から7時30分までの時間帯に登園している園児の数は、全7園合計で1日平均3名程度という状況でございました。これらに加え、事業の実施に向けては、人材や場所の確保、さらには、財政的な課題もあることから、本モデル事業の結果や他自治体の実施状況を踏まえた上で、今後の需要や社会情勢等を見極めながら、引き続き、調査・研究してまいりたいと考えております。
【宮内の再質問①】
ご答弁ありがとうございました。それでは順次、再質問をさせていただきます。朝の居場所づくりについて、今後どのようにニーズを把握していくのかを伺います。例えば、保護者が子どもより早く出勤し、子どもを一人で登校させている家庭もすでにあると思いますが、こうした事情は家庭の外からは分からないものです。また、時短勤務をフルタイム勤務に戻せず、本来の働き方やキャリアを諦めている保護者も確実に存在していると思われます。こうした“潜在的なニーズ”は表面化しにくいですが、本市は今後どのように実態を把握していく予定かお伺いします。
【戸田市のご答弁】
議員ご指摘の「朝の小 1 の壁」問題への対応を検討するに当たっては、来年度、小学校に入学する保育園児の保護者の方を主たるニーズの対象と捉えておりますことから、先ほどの答弁で申し上げたとおり、まずは園児の登園状況により、把握してまいります。
【宮内の再質問②】
続いて再質問します。和光市では、今年6月の平日9日間、朝7時半から8時に「おためし」で朝の居場所を開設しました。これは実際の利用者から直接声を聞き、ニーズを調べることが目的だったと考えられます。戸田市においても、まずはどの程度のニーズがあるのか、また利用者がどのような支援を求めているのかを把握するために、和光市のように試行的に「朝の居場所」を開設していただきたく考えますが、今後ぜひ検討していただけますでしょうか。
【戸田市のご答弁】
議員お話の、和光市の朝の居場所づくりの試行については、本年6月に市内の小学校1校で、市職員による見守りと居場所から学校までの送りという形により、10日間実施されたと把握しております。 本市において実際に試行を検討するに当たっては、人員や居場所の確保などコスト面でも課題が多いことから、まずは園児の登園状況とともに、今年度モデル事業を実施している志木市や、都内への通勤の状況などで本市とも近い環境にある和光市での試行の状況などについて情報を得て、研究してまいります。
【宮内の発言】
最後のまとめに入ります。本来であれば、フレックス制度や多様な働き方は、社会全体で取り組むべき課題です。しかしながら、子育て世代のニーズに対し、柔軟な働き方がまだまだ追いついていないのが現状です。したがって、社会が成熟するまでは、行政がその受け皿となり、働きやすい支援制度を整えていくことが、今まさに地方自治体に求められています。
多くの母親は「子育てが落ち着いたら、もう一度しっかり働いてキャリアを伸ばしたい」と願っています。けれども現実は、キャリアアップのチャンスと子育て期とがちょうど重なり、自分の夢や希望を諦めざるを得ないのが現実です。特に、子どもが小学校に上がったら本格的にフルタイム勤務に戻したいと思っている親は多いので、先ほどのご答弁にありました、保育園の登園状況を見るだけでは潜在的なニーズまでは掴めません。いま制度がないから利用できないのであって、制度ができれば、必ず利用したい人たちが増えていきます。
私自身、子育てを通して痛感しています。子どもが小さいうちはなるべくそばにいてあげて、やがて条件が整ったら働こうと思っていても、すべての条件がそろう時は永遠にやってきません。そのため多くの親は、不完全な状況の中でも、どこかで飛び込み、保育園や学童保育室などの助けを借りながら仕事と子育ての両立をしていますが、現実は、綱渡りのような毎日です。子育ても仕事も待ったなしであり、その時その時で何とかやっているのが現実です。「女性活躍」という耳障りの良い言葉がありますが、現実は、個人の努力だけでは越えられない大きな構造上の壁が、今も依然として立ちはだかっています。
だからこそ今、行政の力が必要です。埼玉県では、志木市のチャレンジに、和光市や行田市も積極的に続こうと努力していますが、子育て世代の多い戸田市こそ、真っ先に取り組むべきテーマではないでしょうか。菅原市長のリーダーシップを発揮していただき、まずは試行的にでも朝の居場所づくり事業を始め、潜在的な市民ニーズに応えて欲しいと思いますし、戸田市に多くいる共働き家庭が安心して朝、子どもを学校に送り出し、親も自分の夢やキャリアを諦めることなく幸せに暮らせる街にしていただけますよう、強く要望させていただきまして、件名2を終わります。